
SOLIZE PARTNERS株式会社
代表取締役社長
井上 雄介
大学院修了後、本田技研工業株式会社に入社し、オートバイの開発に16年間従事。市販オフロードレース用車両や、世界選手権用ワークスマシンの開発責任者などを担当。PwCコンサルティング合同会社にて製造業のDX化などを担当したのち、SOLIZE株式会社に入社し、おもにものづくり領域の事業をリード。2025年7月から現職。
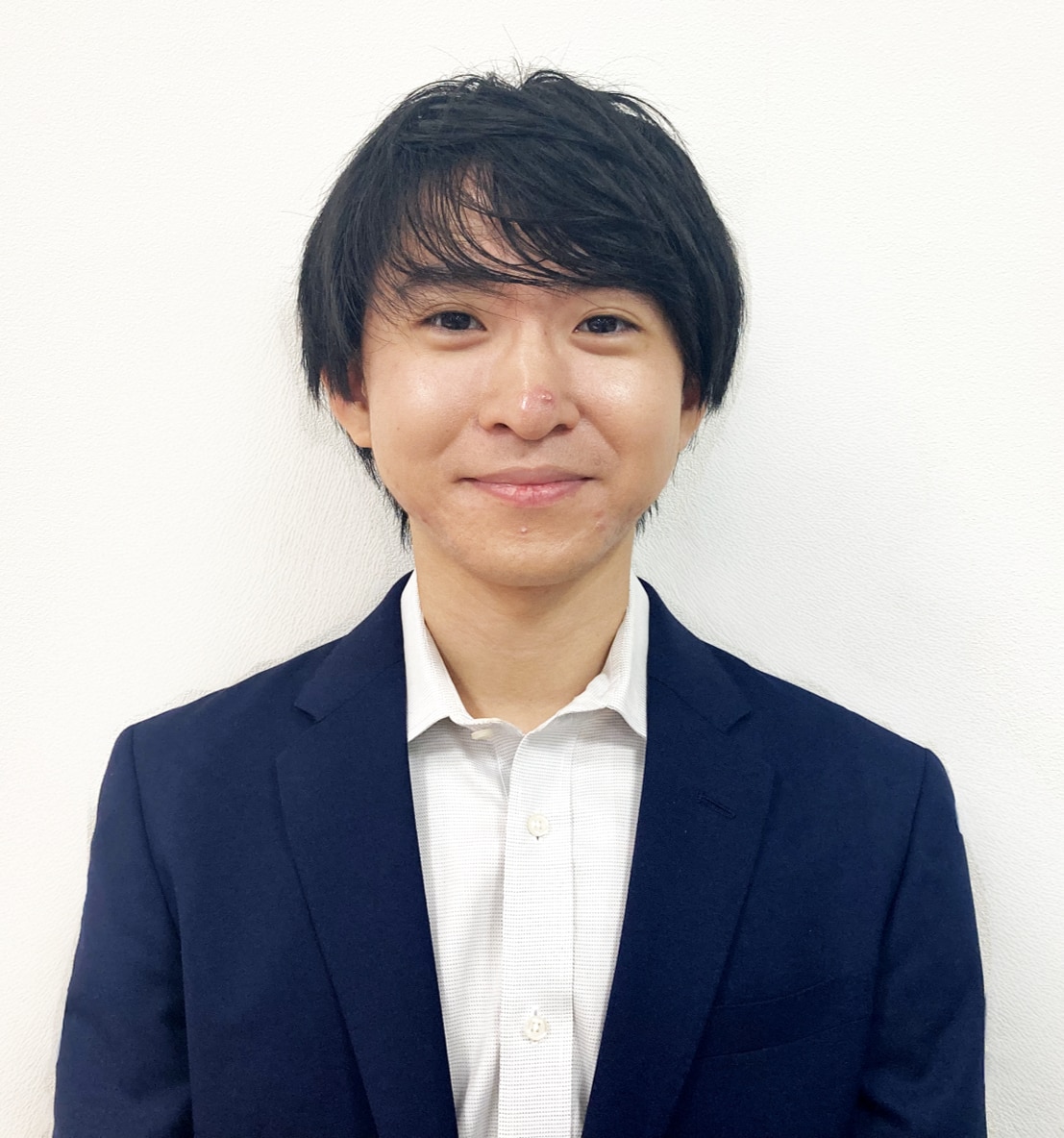
株式会社EQUES
代表取締役/CEO
岸 尚希
東京大学大学院、元松尾研プロジェクトマネジャー、松尾研起業クエスト1期生。
松尾研チーフAIエンジニアとして企業との共同研究に従事。その後、現実世界と情報学の融合を志し,計数工学科在学時に株式会社EQUESを創業。専門はシステム情報学、特にテラヘルツ波通信とハプティクス(触覚技術)。

SOLIZE PARTNERS株式会社
SOLIZE開発統括部
デジタルイノベーション開発部 部長
山田 勝志
大手IT企業で組込みサービス事業責任を担い、オフショア活用による収益改善と組織運営を主導。コンサル案件では世界初のコネクテッドカー向けリモートハッキングコンテストで仮想車両ECU開発をリード。2025年より現職、生成AI・機械学習・フィジカルAIで新サービスを推進。

株式会社EQUES
プロジェクトマネージャー
村山 浩理
東京大学情報理工学系研究科博士課程に在籍。専門は機械学習の理論。EQUESではAIを活用した課題解決のPoCやAIシステム開発プロジェクトをリード。本プロジェクトでは、設計ナレッジの提案支援や3D CADデータの自動生成などのプロジェクトを推進。
株式会社EQUESとの協業について
株式会社EQUES(以下、EQUES)は、東京大学松尾・岩澤研究室発のAIスタートアップとして創業し、品質保証やものづくり領域の高度な課題解決に取り組んでいます。生成AI・大規模言語モデル(LLM)・数理最適化を駆使し、独自のソリューションを提供しています。
自社内で基盤モデルの研究開発を行い、業界特化型の大規模言語モデルを構築するなど、先端AI技術を実用化する力を強みとしています。また、CAD領域における生成AIの開発も進め、設計・解析といったものづくりの現場においても新たな価値を提供しています。

SOLIZE PARTNERS株式会社(以下、SOLIZE PARTNERS)はEQUESのAIスペシャリストと協業し、「未来のものづくり」を見据えたプラットフォームの実証として、設計ナレッジの提案支援や3D CADデータの自動生成などを進めています。
このたび、EQUES 代表取締役の岸 尚希氏と、本件の主担当である村山 浩理氏、そしてSOLIZE PARTNERS 代表取締役社長の井上 雄介および責任者の山田 勝志が、神奈川県大和市のGlobal Engineering Center Yamatoに集い、これまでの協業の歩みを振り返るとともに、今後のものづくりにおけるAI活用の可能性について語り合いました。

ものづくりの現場が抱える課題
ものづくりに AI を活用しようと思ったきっかけは何ですか?

SOLIZE PARTNERS 井上:私たちがAIを設計に本格的に活用しようと考え始めたきっかけの一つは、日本のエンジニアリング分野における深刻な人手不足の問題です。
現在、自動車をはじめとした製造業全体で、ソフトウェア開発へのシフトが進んでいます。一方で、たとえば自動車産業において「エンジンの開発はもうやめてよいのか」と問われれば、決してそうではありません。依然として十分なマーケットが存在しており、そのニーズに応えることが求められています。結果として、我々のようなエンジニアリング会社に対して、「限られた人員で、より高度な開発を担ってほしい」という要望が強まってきました。
しかし現実には、その期待に応えられるだけの技術者が物理的に不足しています。加えて、日本は少子高齢化の流れを避けられず、経験豊富なベテランエンジニアは引退し、若手の担い手も限られてきています。こうした背景のなかで、「人間の代わりに設計の一部を担ってくれるAIがあれば、産業全体に大きな変化をもたらせるのではないか」と直感したことが、AI活用に踏み出す大きなきっかけになりました。
また、実際の設計現場では、現在でも多くの作業が“ベテランエンジニアの勘と経験”に依存しています。設計要件のチェック一つとっても、何千項目にもおよぶチェックリストを、一つひとつ人の手で確認する必要があり、それだけで数日を要することもあります。「こうした作業を、少しでも自動化できないか」という思いは、私自身が現役の設計開発者だった頃からずっと抱いてきた願いでもあります。
そうした積年の課題感と、社会的な構造変化が重なったことで、AIによる設計支援の可能性を本格的に追求し始めました。
AI 活用の実態と業界ニーズ
ものづくり分野での AIの役割やニーズはどのようなものがありますか?
EQUES 岸氏:ものづくり分野におけるAIの役割は、近年ますます多様化・高度化しています。企業ごとのニーズも細分化されており、もはや汎用的な機能だけでは対応が難しい状況になっています。そのため、「個別の業務課題に合わせてAIを活用したい」というニーズが一層高まっていると感じます。
特に製造業では、経験や勘によって得られた知見が属人化してしまい、それが「暗黙知」として組織内に埋もれているケースが多く見られます。こうした知見を「形式知」として整理・共有し、継続的に活用・更新できる状態を作ることは、組織の持続的成長において非常に重要です。
しかし現実には、必要なデータが各所に点在している、そもそも人の頭の中にしか存在しないなど、多くの障壁が存在します。こうした暗黙知や分散した情報をAIの力で引き出し、構造化・可視化していくことは、今後のAIに求められる大きな役割の一つです。

具体的なニーズとしては、「製造工程の最適化」や「品質管理の高度化」に関する相談が多く寄せられています。たとえば、在庫推移やリードタイムを考慮しながら複雑な工程表を Excel で手作業している現場では、「この作業を AI で効率化できないか」といった要望があります。
品質面でも、業界ごとに異なるルールや文書体系が存在し、トラブル発生時の対応や品質文書の作成に多くの時間と労力がかかる場合があります。こうした業務の効率化や、担当者の負担軽減は、AI 活用の大きな目的の一つです。最近では、単なる業務効率化にとどまらず、「製造工程の一部を見直して、より品質の高い製品を作る」「歩留まりや粗利率を改善する」など、現場の“質”を高める観点でAIを導入する動きも増えています。これは、ものづくりの現場において、AI の可能性がさらに広がっている証だと考えています。
設計領域におけるAI活用の壁と、その先にある可能性
設計・ものづくりの分野で AI を使う際、どのような難しさを感じていますか?
岸氏:言語生成AIやChatGPTのような汎用性の高い技術は近年非常に発展しています。ただし、設計分野では3D CADデータなど専門的な環境で使える汎用的な技術はまだ十分とは言えません。現状の生成AIやChatGPTだけでは不十分で、現場で実際に使えるソリューションを開発するためには追加の技術開発が必要です。つまり、現場に適したAIツールや機能を作り込む体制を整えることが不可欠だと考えています。
井上:ものづくり分野でのAI活用には大きな可能性があると思います。ただ、言語処理系の技術が先行しているのは明らかで、プログラミングや文書作成など言語処理が中心の作業はAIによって大幅に効率化できるでしょう。しかし、ものづくりの現場には実物や作業現場があり、人間が介在しなければならない作業も多いのが現実です。その一方で、現場にはまだ多くの隠れたノウハウが存在しており、AIの適用余地は非常に大きいと思います。
取り組み内容:設計ナレッジの提案支援と3D CADデータの自動生成
主な取り組み内容:
1.設計ナレッジの提案支援
特定の形状データから特徴を抽出し、それをもとに設計ナレッジを自動で提案するAIの実現性を検証しました。従来のように過去資料や文献を検索する手間をかけずに、設計のヒントを得られるようになり、知見の再利用性が大きく高まりました。
2.3D CADデータの自動生成
自然言語による指示からAIが適切な3D CADデータを生成できるかどうかを検証しました。その結果、単純な形状や構成であればAIによる自動生成が可能であることを確認しました。 一方で、複雑な形状を扱う際には、構成部品となる要素データを事前に十分整備しておく必要があることも明らかになりました。
A

SOLIZE PARTNERS 山田:私はSOLIZE開発統括部に所属し、社内の技術力を活かしながら新技術と組み合わせて、新たなソリューションやサービスを創出することをミッションとしています。
3年前にChatGPT 3.5が登場した際、「AIで3DデータやCADを扱えるようになれば、社会課題の解決に貢献でき、少人数でも大幅なリードタイム短縮が可能になるのではないか」と考え、試みを始めました。
その過程で、「一緒に開発してくれるパートナーはいるだろうか」と探していたところ、EQUESさんと出会いました。私たちから「このような取り組みは可能か」と提案したところ、「ぜひ一緒にやろう」というお返事をいただき、今回の協業がスタートしました。この取り組みは、一社だけでは乗り越えられない壁をEQUESさんのようなパートナーと協力して突破できる点に、大きな意義があると感じています。
EQUES 村山氏:画像や言語の分野では、10年ほどでAIの活用が進み、スマートフォンでも広く使われています。しかし、これを3Dや部品設計のタスクに適用することは技術的な課題が大きく異なります。特にCADの自動生成に関する取り組みは、この1年ほどで急速に進展し、ようやく成果が見え始めています。2〜3年前には難しかったことが、現在では実用の一歩手前まで来ていると感じています。
井上:2年ほど前、自動設計の可能性を模索していた際、「2 次元設計までは対応できても、3 次元設計は計算処理の壁が厚い」と聞いていました。それに比べて、今こうして成果が見え始めているのは、非常に驚異的な進歩だと感じています。
村山氏:正確には、まだ「完全に自動化できた」という段階には至っていません。ただ、人間の目で見て「これはできたかもしれない」と判断できるレベルには達しています。3Dデータは構造が非常に複雑で、機械が扱いやすい形に変換する方法や、情報量の調整が大きな課題でした。近年の言語・画像技術の進展を基盤に、複雑なデータを一括で処理する技術が生まれ始めており、ようやく実用の領域に近づいていると認識しています。
苦労・チャレンジの裏側
開発当時、苦労された点はありますか?
山田:主な苦労は大きく二つありました。まず一つ目は、AI技術のプロフェッショナルとものづくり現場の技術者との間にある相互理解や歩み寄りの壁です。お互いの専門性が異なるため、共通言語を作りながら開発を進めるのは簡単ではありませんでした。
もう一つは、技術の進歩が非常に速いことです。今日開発した技術が明日には古くなってしまうかもしれない不安や、Googleなどのビッグテック企業が類似技術を次々と発表してくるプレッシャーも強く感じていました。ただし、データ活用の根幹部分には普遍的な価値があるという確信があったことが、開発を続ける大きな支えになりました。
村山氏:技術の進展スピードの速さは本当に驚異的です。NeurIPSのような大規模な国際会議には毎年何万本もの論文が投稿され、その中から数千本だけが採択されます。このような激しい競争環境の中で最新技術をキャッチアップし続けるのは容易ではありません。
さらに、自分のアイデアが他者に先を越されているのではないかという不安も常に付きまといます。だからこそ、技術者の知見を活かしたAI構築や、技術者とコミュニケーションできるAIづくりが開発の鍵だと感じています。

山田:開発の過程で、論文アーカイブを見ながら「この新しい手法が出てきたが、現在進めている方法で本当に大丈夫なのか?」と何度も相談しました。その都度、EQUESさんから「まだ実証されていない技術であり、私たちは別のアプローチで着実に進めています」と明確に説明いただき、安心して共同開発を進めることができました。
また、弊社の井上も「ベテランの知見に簡単に取って代わるものではない。だからこそ、まずは挑戦しよう」と励ましてくれたことも大きな支えでした。この二つの言葉が、開発を続ける原動力になりました。
村山氏:技術が複雑に見えても、根幹となる要素はせいぜい4〜5本程度であり、それらの派生形として進化していくことがほとんどです。業界では、十分にテストせずに部分的な成果だけをリリースする動きも見受けられますが、私たちは慎重に品質管理を行いながら開発を進める必要があると痛感しています。
井上:本当にその通りです。日本の産業界でこれほど急速な技術変化が起きる時期は過去になかなかありません。短期間で産業構造が変化する可能性を間近で見つつ、技術者としてその変化に関われることに大きな喜びを感じています。
国内外のギャップと日本ならではの強み
日本と海外での AI 活用にはどのような違いがありますか?
岸氏:基盤モデル、たとえば大規模言語モデルの分野で見ると、日本と海外では投資規模やリソースの投入量に大きな差があると感じています。日本としては海外の技術に頼る選択肢もありますが、それと同時に、日本独自の要素を取り入れたモデルの開発も重要だと考えています。たとえば日本語に特化した性能の向上や、日本の文化・環境に適したモデルの構築です。
さらに、海外と競争するためには、現場で得られるデータをどれだけ取り込めるかが鍵になると思います。

井上:最近、日本語に特化した翻訳AIが高い精度を実現している事例を目にしました。製造業の中にある暗黙知をAIに取り込むことができれば、逆に海外市場でも通用する可能性が十分にあると感じています。
少し具体例を挙げると、私がオートバイ開発に携わっていた頃、テストライダーがフレームに直径コンマ数ミリの穴をあけて「これで性能が変わるから図面に反映してほしい」と言ったことがありました。信じられないかもしれませんが、そのわずかな違いの積み重ねが性能に影響を及ぼすことがあるのです。こうした暗黙知が日本のものづくりには多く存在しており、それをAIで可視化・活用できれば海外と十分に競争できると考えています。
岸氏:蓄積された知見や暗黙知を強みに変えていくことは非常に重要です。特に製造業とAIの相性が良い分野として、フィジカルAIやロボット、自動化などがあります。現場でどのような動作が行われているのか、どのようなデータが生成されるのかが非常に重要で、それらを有効活用していくことが今後の鍵になると考えています。
ものづくり×AIが拓く未来
未来についてどのようにお考えですか?
岸氏:現場データの活用という視点で見ると、現在は言語や画像分野で汎用モデルが登場しています。しかし、設計分野の3Dデータや自動化・ロボット分野など、ものづくりの現場に特化したモデルが今後ますます出てくると考えています。ものづくりはあらゆる産業の基盤であり、建築も含め物理的なモノを扱うすべての分野が該当します。
その中心にCADや3D技術、自動化技術が位置づき、それが幹(コア)となって自動車や建築など各分野に特化したモデルやツールが展開されていく。こうした「ものづくり × AI」が強固な幹となり、その幹を太く強くしていくことで、日本の産業全体が明るい未来を迎えられるのではないかと思います。
井上:ものづくりとAIの組み合わせは、現在の労働者不足や品質管理、精度向上、性能アップといった課題解決に大きな力を発揮するでしょう。しかし、私が最も期待しているのは、これまでにない新たな価値を創出する力です。「世界初」や「人類初」といった革新的な成果が、ものづくりとAIの融合によって次々と生まれ、人々の生活がより豊かになる未来を強く望んでいます。AIは人間が思いつかないような組み合わせやパターンを生み出す能力を持つ可能性があり、これまで何十年もかけて実現してきた「人類初」への挑戦が、もっと頻繁かつ高速に起こることも考えられます。
そのとき、人々が豊かになる速度はこれまでとは比べ物にならないほど速まるのではないかと強く期待しています。
岸氏:技術進歩が加速していく未来は、AI の力によって十分実現可能だと考えています。
井上:EQUES さんには、この道を切り拓いていただきたいと思います。日本だけでなく、世界のものづくりがよくなる未来を願い、心から期待しています。

※3DEXPERIENCE、Compass アイコン、3DS ロゴ、CATIA、BIOVIA、GEOVIA、SOLIDWORKS、3DVIA、ENOVIA、EXALEAD、NETVIBES、MEDIDATA、CENTRIC PLM、3DEXCITE、SIMULIA、DELMIA およびIFWE は、アメリカ合衆国、またはその他の国における、ダッソー・システムズ (ヴェルサイユ商業登記所に登記番号B 322 306 440 で登録された、フランスにおける欧州会社) またはその子会社の登録商標または商標です。
※Ansys®、及びその他すべてのANSYS, Inc.の製品名は、ANSYS, Inc.またはその子会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
※BETA CAE Systemsの会社名および製品の商標、商号、ロゴは、スイス、欧州、米国、およびその他の国の法律に基づき保護および/または登録されている場合があります。無断での使用または複製は固く禁じられています。
※出典:アルテアエンジニアリング株式会社
©2026 SOLIZE PARTNERS Corporation. All rights reserved.




